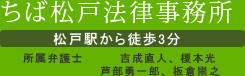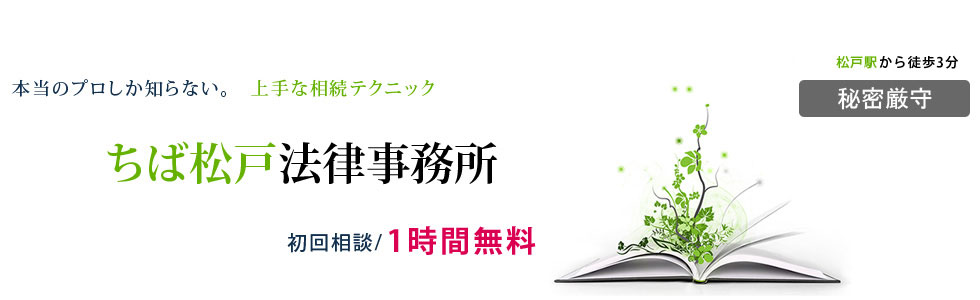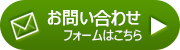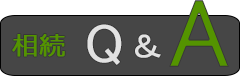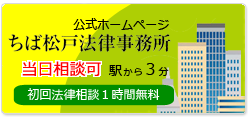遺産分割で揉めないために!弁護士が解説するスムーズな進め方
亡くなった方の財産は相続人間で分配することになりますが、どのように分配するかは相続人間の話し合いによって決まります。
遺産の額が大きいと親族間での争いが激しくなる恐れもあり、場合によっては数年かけても妥協点が見い出せない場合もあるでしょう。
この記事では、遺産分割の流れや相続人間で揉めないための方法などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人間で分配することを指します。
相続人や相続人それぞれの取り分については法律で細かく規定されているため、基本的にはこの”法定相続分”に従って財産を分割することになります。
一方で、相続人間で合意できるのであれば、法定相続分によらずに相続人間の話し合いによって決めることも可能です。そのため、場合によってはお互いの主張が激化し、交渉がまとまらない場合があります。
【遺産分割がまとまらないケース】
・遺産の中に不動産が含まれていて分配方法で揉めるケース
・生前被相続人の世話をしていたことなどから自身の取り分を多めに主張してくるケース
・昔から力を持っている親族など法定相続人ではない親族が自身の権利を主張してくるケース
・特定の相続人に全財産を相続させると遺言書に書かれていたケース
・相続人が行方不明で遺産分割協議がまとめられないケース など
遺産分割がまとまらない場合には、法定相続分での分割を主張するのが原則ですが、場合によっては適切な解決に至らない場合もあります。そのまま放置しても問題の解決にはならないので、早い段階で弁護士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
遺産分割の流れ・手順
遺産分割のおおまかな流れ・手順は次の通りです。
● 遺言書の有無を確認する
● 相続財産を確定させる
● 遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する
● 話し合いがまとまらなければ遺産分割調停を行う
● 調停不成立なら遺産分割審判も検討する
相続人を確定する
遺産分割をするためには、遺産を相続する”相続人”を確定させる必要があります。
この相続人は親族なら誰でもなれる訳ではなく、民法で細かく規定されています。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第1位 | 子ども |
| 第2位 | 直系尊属(両親、祖父母) |
| 第3位 | 兄弟・姉妹 |
※ 配偶者は相続放棄をしない限り常に相続人となります。
たとえば、被相続人の配偶者と子どもが法定相続人として遺産を引き継ぐ場合には、両親や兄弟姉妹は遺産を引き継ぐ権利を有しません。この場合、第1順位の相続人である子どもがいない場合や、子どもが相続放棄をして初めて、それ以降の順位の相続人に相続する権利が回ってくることになります。
遺産分割をする場合、相続人となる人全員の同意を得る必要があるので、まずは相続人を確定させる必要があります。すでに相続人が亡くなっている場合、その下の世代に相続権が移る”代襲相続”と呼ばれる規定もあるので、慎重に相続人を確定させる必要があります。
複雑な相続の場合には相続人が数十名になるケースもあり、連絡を取ったことがない方やそもそも顔も名前も聞いたことがないような方が相続人になっている場合もあります。相続人の確認漏れがないよう戸籍謄本等を取得し正確に現状を把握しましょう。
遺言書の有無を確認する
被相続人が亡くなったら、遺言書があるかどうかも確認する必要があります。遺産分割において遺言書の内容は優先的に考慮されるからです。
遺言書には、被相続人本人が作成した「自筆証遺言」、公証役場にて作成・保管する「公正証書遺言」、遺言書の内容を非公開にしておく「秘密証書遺言」の3種類があります。
自宅に遺言書が保管してあれば問題ないですが、生前に遺言書の存在を聞いていたにもかかわらず自宅で見つからない場合には、公証役場で保管されている可能性を疑って照会をかける必要があるでしょう。
また、公正証書遺言などの一部の遺言を除き、遺言を見つけたら裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
もし遺言書が自宅や公証役場で見つからない場合でも、法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用している可能性があります。この制度では、被相続人が生前に自筆証書遺言書を法務局で保管している場合があり、必要に応じて法務局に照会することで内容を確認できます。
法務局で保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、スムーズに手続きが進められる利点があります。遺言書が見つからない場合には、この制度を利用しているかどうかを確認すると良いでしょう。
相続財産を確定させる
遺産分割を適切に行うためには、遺産全体を正確に把握する必要があります。
ここで確定させるべき遺産は、預貯金や不動産、株式などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含みます。
もしプラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに大きければ、家庭裁判所に相続放棄をすることも検討する必要があるでしょう。また、遺産全体の把握が困難であれば、限定承認と呼ばれる相続方法を選択することも考えられます。
相続財産は、被相続人の預金通帳や公的機関から届いている通知などから確定させていきます。遺産分割を行ったあとに別の遺産が出てくると、1度まとまった協議もやり直しになる可能性があるので注意してください。
遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成する
相続人および遺産の全容が把握できたら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人間で遺産をどうやって分配するかを決める話し合いのことです。誰がどれくらいの割合で遺産を相続するかを決める話し合いを行います。
基本的には法定相続分通りに分割するのが基本ですが、分割方法が難しい不動産が遺産に含まれている場合や、生前被相続人を世話していたなどの関係から取り分を多く主張してくる相続人がいる場合には、交渉が難航する恐れがあります。
また、特定の相続人が遺産の情報を開示してくれない場合もあり、その場合には交渉だけではなく裁判所を通した手続きが必要になる場合もあるでしょう。
遺産分割協議で話し合いがまとまったら、遺産分割協議書と呼ばれる合意書を作成します。この書面がないと合意内容についてあとあとトラブルになる恐れもあるので、記入漏れがないよう正確に作成しましょう。
話し合いがまとまらなければ遺産分割調停を行う
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合、遺産分割調停を行うことも検討します。
遺産分割調停では、裁判所の調停委員が間に立ち、話し合いでの問題解決を目指します。専門的な知識を持った調停委員が双方の主張や証拠などを総合的に判断したうえで、解決案を提示したり必要なアドバイスをしてくれます。
当事者だけでは感情的な面から話し合いが難しいケースも多いですが、第三者が客観的な立場でアドバイスをしてくれることで、話し合いがスムーズにいくケースも珍しくありません。
ただし、遺産分割調停はあくまでも話し合いでの解決を目指す手続きです。裁判のように裁判官が判断してくれるわけではないので、妥協点を見出せないようなら調停は不成立となり、審判手続きへと移行します。
調停不成立なら遺産分割審判も検討する
遺産分割調停でも話し合いがまとまらず調停不成立になった場合には、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。
遺産分割審判では、当事者の主張や提出された証拠などから裁判官が遺産分割に関する決定を下します。調停のように話し合いでの解決を目指す訳ではないので、遺産分割を強制的に進められるメリットがあります。
遺産分割協議で有利な決定(審判)を受けるためには、客観的な証拠の有無が重要となります。特別受益や寄与分など、法定相続分に依らない遺産の分割を望むのであれば、その分割方法が適切であることを証明する証拠を提出する必要があります。
遺産分割調停では、審判までに4〜5回程度以上が開かれるケースが多いです。審判に移行してからも解決までに1年以上かかるケースも珍しくないので、時間をかけずに手続きを進めたい方は遺産分割協議の段階で話し合いをまとめるのがおすすめです。
審判が確定したらその内容通りに遺産分割を行うことになりますが、内容に不服がある場合、2週間以内であれば即時抗告を申し立てることも可能です。
遺産分割で揉めないための方法
遺産分割はお金が絡む問題です。生前は仲の良かった親族同士でも、お金の話になった途端話が拗れるケースも珍しくありません。
ここでは、遺産分割で揉めないための方法を3つご紹介しますので、しっかり把握して余計なトラブルを起こさないようにしましょう。
● 遺言書・生前贈与・家族信託などの生前対策
● トラブルがあるなら早めに弁護士に相談を
相続人間でコミュニケーションを取っておく
被相続人が亡くなった時に揉めたくないのであれば、生前から相続人である親族と良好な関係を築いておくようにしましょう。
相続人とコミュニケーションを密に取っておけば、相続開始後に感情的な溝を原因として生じる争いを避けることができるでしょう。遺産分割の方法で多少折り合いがつかなかったとしても、お互い意地になることも少なく交渉が短期間でまとまる可能性が高くなります。
“良い相続”のためにも、相続人となる親族とは仲の良い関係を保っておくのが良いでしょう。
遺言書・生前贈与・家族信託などの生前対策
生前対策をしっかりしておけば、亡くなったあとに親族が揉めるのを防ぐことができます。
生前対策にはさまざまなものがありますが、遺言書であれば遺産分割方法についての指定を行うことができます。相続する権利のない親族が自身の権利を主張してきたり、根拠のない遺産分割が行われるのを防げるので、相続人間での争いを未然に防ぐことができるでしょう。
また、公正証書遺言であれば裁判所での検認が不要なので、遺産の中に不動産がある場合でもスムーズに相続登記などを行うことができます。
他にも、生前贈与で自身の財産を整理したり、家族信託で財産を相続する人を指定しておけば、相続人間での無用な争いを避けることができるでしょう。
生前対策にはさまざまな種類のものがあるので、どういう対策を取るべきか迷ったら専門家である弁護士に1度相談することをおすすめします。
トラブルがあるなら早めに弁護士に相談を
遺産分割で争いが起きたり生前対策を行いたいと考える場合には、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。
法律の専門家である弁護士であれば、揉めている原因を法的に分析して適切なアドバイスをすることができます。また、相続人や遺産の調査、調停・審判の手続きの代理や遺産分割協議書の作成など、面倒な手続きを全て任せられるのも弁護士に依頼する大きなメリットの1つです。
遺産分割で揉めた場合、当事者間での話し合いではお互いにヒートアップしてしまい、話し合いが平行線を辿ってしまうケースも珍しくありません。弁護士が間に入れば、法的な見解を主張することですんなり交渉がまとまるケースも少なくありません。
生前対策に関する相談から複雑な相続に関する相談まで何でも相談できるので、当事者間での解決が難しいと感じたらなるべく早めに相談するようにしましょう。
まとめ
遺産分割で揉めないためには、相続人間でコミュニケーションを密に取っておくことと、生前対策をしっかり行っておくことが重要です。
また、もし揉め事が起きてしまった場合にはなるべく早めに弁護士に相談することも重要です。
“良い相続”をするためには、相続に関する正しい知識が必要です。複雑な相続では、法律や判例だけでなく他の相続人を納得させるだけの交渉スキルも必要になってきます。
本来争う必要のない親族間での争いは精神的ストレスが大きいので、困ったら弁護士に相談していち早く問題を解決することをおすすめします。