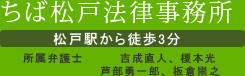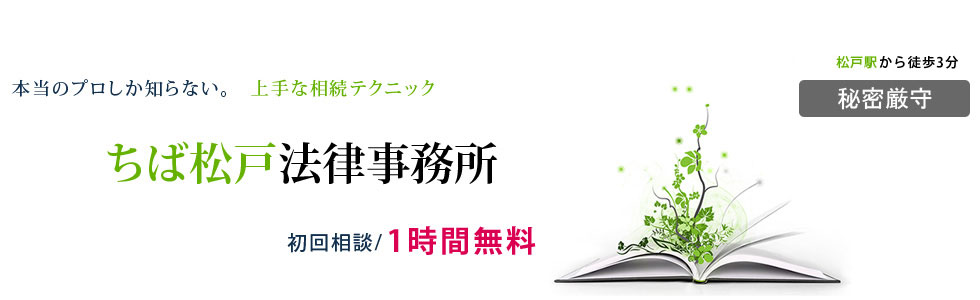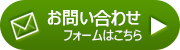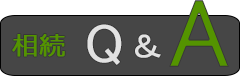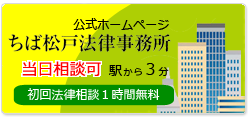成年後見についてわかりやすく解説。メリットや手続き方法についても説明します。
ご家族が認知症や精神障害などで、預貯金の管理や不動産の売買契約など支障をきたすことがあります。こういった場合にご家族が法律行為などをサポートできる制度を成年後見制度といいます。今回は成年後見のメリットや手続き方法などについて解説します。
成年後見って何?
冒頭でも少し解説しましたが、ご家族が認知症や精神障害などで判断能力が低下してしまい、預貯金の管理や不動産の売買契約などの法律行為に支障をきたすことがあります。こういった場合にご家族が法律行為などをサポートできる制度を成年後見制度といいます。
成年後見には、法律上の後見制度である法定後見と公正証書で任意後見契約をする任意後見があります。
まずは、法定後見から解説します。法定後見には、後見、保佐、補助の3種類あります。具体的には以下のとおりです。
①後見
後見とは、常に判断能力が欠けており、多くの手続き・契約などを1人で決めることが難しい人です。
②保佐
保佐とは、1人で判断する能力が著しく不十分で、重要な手続きや契約など1人では決められない人です。
③補助
補助とは、1人で判断する能力が不十分で、重要な手続きや契約をする時に1人で決めることに心配がある人です。
法定後見の手続き(申立)方法
法定後見の手続き(申立)方法は以下のとおりです。
①手続き場所
本人(認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断能力が十分ではない人)の住所地の管轄家庭裁判所で手続きをします。
②手続きをできる人
手続き(申立)をできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人・保佐人・補助人、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人、市区町村長、検察官などです。
なお、4親等内の親族とは、以下の人をいいます。
・親、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫
・兄弟姉妹、おじ、おば、甥姪、いとこ
・配偶者の親、祖父母、曾祖父母、子、孫、ひ孫
・配偶者の兄弟姉妹、おじ、おば、甥姪
③手続き(申立)する時の主な必要書類
手続きする時の主な必要書類は以下のとおりです。なお、必要書類は提出する時にコピーを取っておくとその後何を提出したか確認ができるのでコピーをとって控えを作っておくといいでしょう。
・後見・保佐・補助開始等申立書
・財産目録及びその資料(預貯金通帳のコピー、保険証券のコピー、株式・投資信託等の資料のコピー、不動産の全部事項証明書、債権・負債等の資料のコピーなど)
・本人の収支計算書など(年金通知書のコピー、株式配当金の通知書のコピー、住宅ローンの領収書(2か月分)のコピー、納税通知書のコピーなど)
・診断書(成年後見制度用)
・本人の戸籍謄本
④手続き(申立)費用
手続き(申立)費用は以下のとおりです。
・申立手数料:800円分の収入印紙
・登記手数料:2600円分の収入印紙
・郵便切手代(例:後見の場合3720円、保佐の場合4920円(2024年7月現在))
・鑑定料
※鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続きです。手続(申立)時に提出する診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定依頼をする形で行われます。後見・保佐の場合は法律上、原則として鑑定が必要ですが、診断書の内容などを総合的に判断して鑑定が省略されることもあります。なお、診断書を作成した医師以外が鑑定人に選ばれることもあります。
鑑定料(鑑定人への報酬)については、一般的に10万円~20万円程度の費用がかかります。
手続き(申立)時の本人・候補者調査
成年後見の手続き(申立)をする時は、本人の意思を尊重するために申立内容などについて本人から意見を直接聞く場合があります。これを本人調査といいます。
本人調査の時は、本人に家庭裁判所に来てもらう場合があります。なお、入院、体調等によって来ることが困難な場合は、家庭裁判所の担当者が入院先の病院に直接伺うこともあります。
また、補助開始や保佐開始で代理権を付ける場合は、本人の同意が必要にとなります。本人調査の手続きで同意の確認も行います。そして、成年後見人など候補者の適格性に関する調査も行う場合があります。
法定後見のメリットとデメリットは?
まず法定後見のメリットは、裁判所が決めた法定後見人が本人の代わりに財産管理や生活などを支援したり、代理で契約してくれたりします。
それでは、主なメリットについていくつか解説します。
①詐欺や余計な契約を防止できる
昨今、高齢者をターゲットにした詐欺や高額な健康器具などを契約させる悪徳業者が増加していますが、法定後見人が本人に代わって契約しますので詐欺や余計な契約を防止できます。また、もし本人が契約してしまった場合でも契約を取り消すことができます。
②財産管理を代理できる
法定後見人は、本人に代わって預貯金の入出金や支払い、定期預金の解約ができます。そのため、判断能力が低下して無駄な買い物が増えるなど、本人の使い込みを防止することができます。
③不動産の売却ができる
土地や家屋など不動産を売却する時に、本人の意思確認をしなければ売却することができませんが、法定後見人は本人に代わって売買契約をすることができます。そのため、不動産の売却が可能です。ただ、居住用の不動産を処分する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
次にデメリットについて、いくつか解説します。
①法定後見人への報酬支払が必要になることもある
子どもなど親族が法定後見人になる場合は無報酬が多いかと思いますが、弁護士など専門家が法定後見人になる場合は、毎月の報酬支払費用が発生します。また、何か特別な依頼をした時は、追加の報酬支払が発生することもあります。
②法定後見人が財産を使い込む可能性がある
子どもなど親族が法定後見人になる場合、本人の預貯金を使い込んでしまうということもあります。そのため親族が財産管理をする場合は「他人の財産を管理している」という意識を持つことが重要です。
③法定後見人の選定には手間がかかる
先ほど、法定後見の手続き(申立)の流れについて解説しましたが、法定後見人を選任する場合は、家庭裁判所に手続き(申立)を行います。そのため、手続き(申立)する時は、戸籍謄本や診断書などの書類を提出する必要があり手間と時間がかかります。
任意後見って何?
任意後見とは、冒頭で少し解説しましたが、判断能力があるうちに、認知症や障害の場合に備えて、財産管理や生活の支援などを代わりにしてもらいたいことを決めておくことを任意後見といいます。そして、あらかじめ本人自らが決めた人を任意後見人といいます。任意後見は、公証人の作成する公正証書によって締結されます。
任意後見の手続き方法
任意後見の手続き(申立)方法は以下のとおりです。
①手続き場所
本人の住所地の管轄家庭裁判所で手続きします。
②手続きできる人
手続き(申立)できる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見人です。なお、4親等内の親族の詳細は、法定後見の手続き(申立)方法で解説しましたので割愛します。
③手続きする時の主な必要書類
手続きする時の主な必要書類は以下のとおりです。なお、必要書類は提出する時にコピーを取ることをおすすめします。
・任意後見の申立書
・任意後見契約公正証書の写し
※任意後見の場合、公証役場で任意後見契約公正証書を作成する必要があります。
・財産目録及びその資料(預貯金通帳のコピー、保険証券のコピー、株式・投資信託等の資料のコピー、不動産の全部事項証明書、債権・負債等の資料のコピーなど)
・本人の収支計算書など(年金通知書のコピー、株式配当金の通知書のコピー、住宅ローンの領収書のコピー、納税通知書のコピーなど)
・診断書
・本人の戸籍謄本
④手続き(申立)費用
手続き(申立)費用は以下のとおりです。
・申立手数料:800円分の収入印紙
・登記手数料:1400円分の収入印紙
・郵便切手代(例:3720円(2024年7月現在))
・鑑定料
鑑定料(鑑定人への報酬)については、一般的に10万円~20万円程度の費用がかかります。
任意後見のメリットとデメリットは?
まずは、主なメリットについて、いくつか解説します
①本人の意思で任意後見人を選択できる
任意後見は、本人の判断能力があるうちに手続きするので、自分で信頼できる人を任意後見人に選ぶことができます。子どもなど親族はもちろん、信頼できる第三者を選択することも可能です。
②本人の希望にそって契約内容を決めることができる
「介護サービスは、在宅がいい、施設に入りたい」「自分が動けなくなったら実家は売却してほしい」など本人の希望にそって契約内容を決めることができます。
③公正証書で契約内容が登記されるので安心できる
任意後見は、公証役場で公正証書を作成し、本人の希望にそった契約内容が登記されるので安心できます。
次にデメリットについて、いくつか解説します。
①任意後見監督人を選ばなければいけない
任意後見では、任意後見人を監督する任意後見監督人を選任しなければいけません。
任意後見人のことを監督するのでメリットでもありますが、任意後見監督人は弁護士などの専門家が選任させることが多いため、毎月の報酬支払いが発生します。
②取消権が認められない
例えば、本人が勝手に数百万円の高額な商品購入や借金などの法律行為をした場合、法定後見人はその契約を取り消すことができますが、任意後見人は、家庭裁判所で手続きを取っていない以上、契約を取り消すことは出来ません。
これは、任意後見人が本人の意思で将来のために後見人予定者を選んでおくための制度だからです。
③亡くなった後の財産管理ができない
任意後見は、本人が亡くなった時に契約終了になりますので、亡くなった後の財産管理や健康保険、年金の行政手続きなどの事務処理を任意後見人に依頼することができません。
なお、任意後見人に財産管理や亡くなった後の事務処理をしてもらいたい場合は、任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結する必要があります。
まとめ
今回は、成年後見、特に法定後見と任意後見のメリットや手続き方法などについて解説しました。成年後見の手続きについて、難しく感じられた人もいるかと思います。手間と労力を考えると弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。