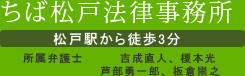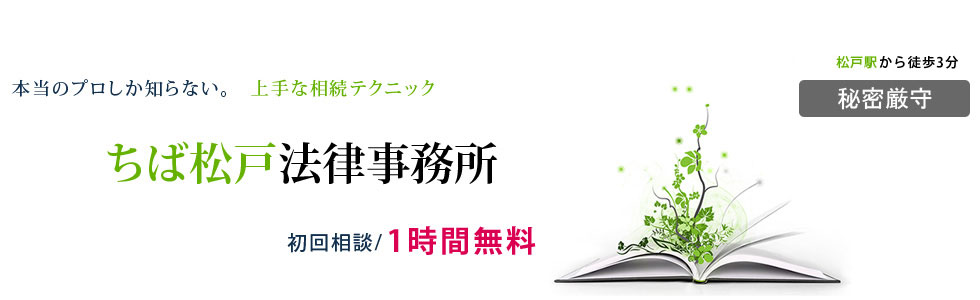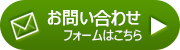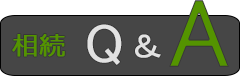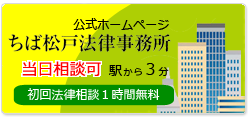相続人が多数いる場合の不動産の分割方法と注意点を解説
ご家族が亡くなった時、建物や土地など不動産を相続する場合もあるかと思います。今回は相続人が多数いる場合の不動産の分割方法と注意点について解説します。
不動産の分割方法
ご家族が亡くなった時、現金や預貯金であれば残された家族(相続人)で法定相続分を分ければよいですが、建物や土地などの不動産を家族で分けるとなると大変です。
そこで、相続人が多数いる場合の不動産の分割方法としては以下の方法があります。
①現物分割
②代償分割
③換価分割
それでは、上記①~③の不動産の分割方法について詳しく解説します。
①現物分割
現物分割とは、不動産をそのまま分ける遺産相続です。例えば、建物が存在する広い土地がある場合、長男が実家の建物と建物の建っている土地を相続して、次男が建物の建っていない土地を分筆(ぶんぴつ)して取得することです。
分筆とは、一筆の土地をいくつかに分けて別の不動産として登記することです。一筆とは、登記上の土地の数を表す単位で、独立した1個の土地をいいます。なお、分筆できるのは土地だけで建物の分筆はできません。
また、注意点としては条例などによって分筆が禁止されている地域もあります。そして、正方形や長方形の土地であれば分筆しやすいですが、台形など形が整っていないと土地が狭くなったり、土地の形が整ってないと建物を建てにくいため、土地の評価額が下がり売却が難しくなるというケースもあります。
さらに、住宅用地に対する特例措置というものがあり、家が建っている土地は固定資産税が軽減されます。ただ、分筆すると家が建っていない土地はこの特例措置が適用されません。そのため、分筆することで、分筆前よりも固定資産税が上がってしまうことということあります。
参考まで、住宅用地に対する特例措置が適用される場合は、固定資産税や都市計画税の課税標準額は以下のとおりとなります。
| 小規模住宅用地の土地面積 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 (200㎡以下) | 6分の1 | 3分の1 |
| 一般住宅用地 (200㎡超える部分) | 3分の1 | 3分の2 |
参考:大阪市HP https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000239753.html
【分筆の例】
父が100㎡の土地を所有→長男が50㎡、次男が50㎡ずつ分筆する
②代償分割
代償分割とは、不動産は1人が相続して、他の相続人は法定相続分の代償金(現金)を支払うことです。
例えば、評価額が3,000万円の建物と土地があり、長男と次男が相続する場合、長男が建物と土地を相続すると次男の相続分が無くなってしまいます。そこで、次男に法定相続分の2分の1の1,500万円の代償金を支払えば遺産分割をスムーズに進めることができます。
なお、注意点としては先ほど解説したとおり、不動産を相続する相続人は代償金を支払うことになりますので相応の資金力が必要になります。そのため、資金力のない相続人には適していません。
また、代償金の金額を決める時は建物や建物などを評価することになります。代償金の金額を決める方法としては、相続税評価額や代償分割時の時価など様々な方法があります。そのため、評価方法によって金額が変わり、相続人同士で代償金をいくらにするかで意見が割れると相続トラブルに発展することもあります。
③換価分割
換価分割とは、不動産を売却して、その売却金を相続人同士で分ける方法です。
例えば、評価額が3,000万円の建物と土地があり、不動産仲介手数料や譲渡所得税などの諸経費が300万円掛かったとします。この諸経費300万円を引いた2,700万円を長男と次男で法定相続分2分の1の1,350万円ずつ分けます。
なお、注意点としては、実家など思い入れのある不動産を売却するわけですから相続人同士で不満が出ないように話し合う必要があります。また、不動産仲介手数料や譲渡所得税などの諸経費が掛かってしまうので、諸経費分が売却金額から減ってしまいます。そして、不動産は売却時期によって金額が上下するため、期待どおりの売却金額になることもあれば、逆に期待したよりもかなり安値で売却するということもあります。
不動産の分割方法は遺産分割協議で決める
先ほど解説した不動産の分割は遺産分割協議で決めます。遺産分割協議とは、ご家族が亡くなった後に遺産がある場合、残されたご家族(相続人)で遺産の分け方を話し合うことです。
一般的に、遺産分割協議は以下①~④の流れで進めます。
①遺言書があるか確認
亡くなったご家族の遺言書がある場合は、遺言書とおりに相続するのが原則です。遺言書があれば遺産分割協議を行う必要もありません。
なお、遺言書がある場合でも、相続人全員で遺産分割協議を行って、遺言書の内容と異なる遺産の分け方をすることも可能です。
②相続人の調査をする
先ほど解説したとおり、遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければならず、誰が相続人なのかを調査しないといけません。このことを相続人調査といいます。
相続人調査をする時は、亡くなったご家族の戸籍謄本を本籍地の役所から取り寄せます。戸籍謄本には、亡くなったご家族の出生から、婚姻、家族関係などが記載されており、戸籍謄本を見れば誰が相続人なのかを確認することができます。
③相続財産を調査する
相続人調査が終わったら、次に相続財産の調査をします。
相続財産には、不動産や現金、有価証券などプラスの財産、住宅ローンや借金などマイナスの財産(負債)があります。相続財産の数や評価をすることを相続財産調査といいます。
今回は、不動産の分割方法の解説ですので、相続財産調査のなかでも不動産の調査方法について解説します。
不動産の調査をする時は、不動産の売買契約書、権利証(登記識別情報・登記済証)などが保管されていないかを確認します。なお、不動産がある場合は、毎年、固定資産税の納税通知書が役所から送られてきますので、納税通知書で確認することもできます。
権利書や納税通知書が見つからない場合は、役所で名寄帳を申請すると所有している不動産の情報が一覧で確認できます。
ただ、名寄帳には市区町村内の不動産しか記載がないため、複数の市区町村に不動産を所有している場合にはそれぞれの市区町村に申請する必要があります。
※名寄帳とは、課税対象になっている土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。
④遺産分割協議書を作成する
先ほど解説した②~③の調査が終わったら、遺産分割協議をして相続人全員が合意すれば遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成方法に特に決まりはなく、パソコンで作成しても、手書きで作成しても問題ありません。
作成する場合は、以下の3つがポイントになります。
・財産の内容と相続人を特定しておく
・相続人全員の名前を記載する
・印鑑証明を受けた実印を押す
なお、不動産の場合は、遺産分割協議書に所在地や面積などを正確に書くことが重要です。
遺産分割協議で結論が出ない場合
先ほど遺産分割協議について解説しましたが、遺産分割協議は相続人全員がスムーズに合意するとは限りません。なかなか結論が出ず長期化することもあり得ます。
このような場合は遺産分割調停や審判で遺産分割を決めることになります。
分割調停は、家庭裁判所の審判官と2人以上の調停委員からなる調停委員会の立ち合いの基に行われる話し合いです。分割審判は、裁判所の審判によって不動産の分割方法を決定します。分割調停の申し立て先は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。分割調停は、調停委員会が相続人一人ひとりの意見を聞き、適切な助言をして、話し合いが合意したら調停調書にまとめます。調停調書は審判と同じ効力を持っているので、これにしたがって不動産の分割を行います。
分割調停で話がまとまらなかった場合は審判を行うことになります。裁判所の審判によって不動産の分割方法を決定するので公平性を保つことができるというメリットがあります。ただ、手間と時間がかかってしまうというデメリットもあります。
まとめ
今回は、相続人が多数いる場合の不動産の分割方法や遺産分割協議で結論が出ない場合の分割調停や審判などについて解説しました。
初めて不動産を相続する場合、相続人同士で分割方法について協議すると言ってもなかなかスムーズには進まないかと思います。手間と労力を考えると、弁護士などに相談することをおすすめします。