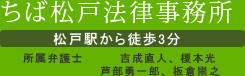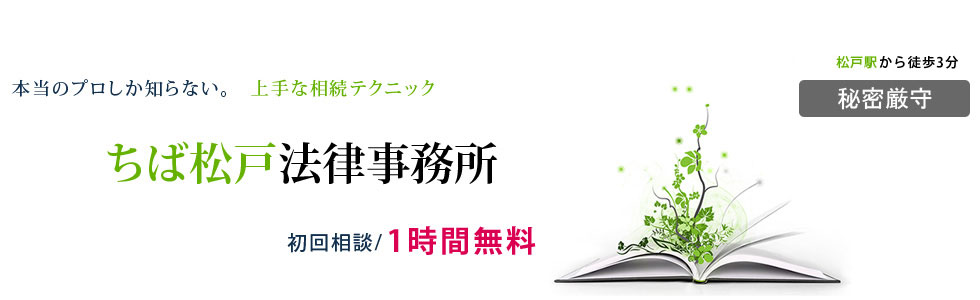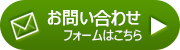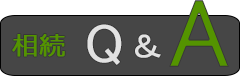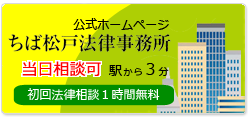相続手続きは自分でできる?専門家に依頼するメリットと費用を紹介
ご家族が亡くなった後はとても悲しい気持ちになりますが、それも束の間、様々な相続手続きが待っています。
今回は、相続手続きは自分でできるのか、そして、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方がメリットがあるのか、などについて解説していきます。
相続手続きって何をすれば良いの?
相続手続きと言っても、ご家族が元気なうちは縁がない話だと思いますが、ご家族が亡くなった後にいざ相続手続きしようと思っても何から手をつけたら良いかわからないという場合もあります。
そこで、ご家族が亡くなった後どのような相続手続きをすれば良いか、解説していきます。
まず、ご家族が亡くなった後、最初にやらなければいけない相続手続きが死亡届を役所に提出することです。
死亡届は、ご家族が亡くなったことを知った日から7日以内に死亡届(死亡届の裏面は死亡診断書になっています)を亡くなったご家族の住所地または届け出する人の住所地の市区町村役場に提出します。死亡届と一緒に死体火葬(埋葬)許可申請書も提出します。死亡届を市区町村役場に提出しないと亡くなったご家族の火葬ができませんので注意しましょう。
ただ、葬儀を依頼する葬儀屋さんが死体火葬(埋葬)許可申請書(死亡届)を葬儀を行うご家族に代わって市区町村役場に提出するのが一般的ですので提出し忘れることは少ないかもしれません。
次に、亡くなったご家族が遺言書を残していないかどうか、忘れずに確認してください。遺言書には財産の内容、財産を誰に相続させるかなどが書いてあります。
亡くなったご家族がすべて手書きで書いた自筆証書遺言を見つけた場合は勝手に開封してはいけません。勝手に開封することは法律で禁止されています。それは遺言の内容が”改ざん”されることを防ぐことが目的だからです。誤って開封した場合は過料(5万円以下)が科されることがあります。
そのため、自筆証書遺言は家庭裁判所で改ざんや偽造がされていないかを確認する検認手続きをする必要があります。
なお、法務局で保管(2020年7月10日から開始)していた自筆証書遺言は、検認しないで開封しても問題ありません。
また、公証役場で作成した公正証書遺言を見つけた場合は、自筆証書遺言のように検認の必要はありません。その場で開封し、内容を確認することができます。
遺産分割はどうすれば良いの?
先ほど、死亡届の提出、遺言書を見つけた場合の相続手続きについて解説しましたが、ご家族が亡くなった後に遺産がある場合、残されたご家族(相続人)で遺産の分け方を話し合わなければいけません。相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議といいます。
なお、自分で遺産分割協議をする時は、次の手順で進めていきます。
①遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺言書通りに相続するのが原則です。遺言書通りに相続することになりますので遺産分割協議を行う必要もありません。なお、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺言書の内容と違う遺産の分け方をすることも可能です。
②相続人が人数を調査する
先ほど解説した通り、遺産分割協議は相続人全員で話し合わなければいけないため、誰が相続人なのかを調査しないといけません。このことを相続人調査といいます。
相続人調査をする時は、亡くなったご家族の戸籍謄本を本籍地の役所から取り寄せます。戸籍謄本には、亡くなったご家族の出生から、婚姻、家族関係などが記載されています。戸籍謄本を見れば誰が相続人なのか確認することができます。
③相続財産がいくらかを調査する
相続財産には、不動産や現金、有価証券などプラスの財産、住宅ローンや借金などマイナスの財産(負債)があります。相続財産がいくらかを調査することを相続財産調査といいます。主な相続財産調査は次の通りです。
<預貯金の調査>
預貯金の調査とは、亡くなったご家族の通帳やキャッシュカードを探し、どこの金融機関と取引していたのかを確認することです。通帳があれば記帳をして亡くなるまで誰と取引していたのかを把握することができます。
金融機関を特定したら残高証明書の発行を依頼します。残高証明書の発行手続きは相続人全員が共同して行う必要はなく、相続人1人でも請求は可能です。
<不動産の調査>
不動産の調査とは、不動産の売買契約書、権利証(登記識別情報・登記済証)などが保管されていないかを確認することです。なお、不動産がある場合は、毎年、固定資産税の納税通知書が役所から送られてきますので、その納税通知書で確認することができます。
また、権利書や納税通知書が見つからない場合は、役所で名寄帳を申請すると所有している不動産の情報が一覧で確認できます。ただ、名寄帳には市区町村内の不動産しか記載がないため、複数の市区町村に不動産を所有している場合にはそれぞれの市区町村に申請する必要があります。
※名寄帳とは、課税対象の土地や家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です
<有価証券の調査>
有価証券の調査とは、亡くなったご家族が有価証券を持っていた場合に、取引していた証券会社から残高証明書を取り寄せすると、どの証券銘柄と株数を把握することができます。
なお、亡くなったご家族が有価証券を持っていたことは知っていても、取引していた証券会社がわからない場合もあります。その時は証券保管振替機構(ほふり)に対して情報開示請求を行うことで、どこの証券会社と取引していたかがわかります。
<負債の調査>
負債の調査とは、亡くなったご家族の持ち物に借用書や借入残高が記載された書類がないか、税金の未納通知書、督促状がないかなど負債(借金)状況を調べることです。
借金の借入先がわからない時は、信用情報登録機関に照会するという方法もあります。国内の信用情報登録機関は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)です。各社のホームページを見ると、信用情報を開示する時の手続き方法や必要書類などが記載されています。
④相続人全員で遺産の分け方を話し合う
相続人と相続財産を把握したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。なお、遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要がありますので、相続人が1人でも欠けた状態で実施すると無効になります。
なお、必ず相続人全員が顔を合わせる必要はなく、例えば、遠方に住んでいるため参加できないといった場合は電話やメールなどを使って話し合うことも可能です。重要なことは相続人全員が遺産分割協議に合意(賛成)しているかどうかということです。
⑤遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議で相続人全員が合意したら、遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議書の作成方法に決まりはなく、パソコンで作成しても、手書きでも問題ありません。作成する時は以下の3つがポイントになります。
・財産の内容と相続人を特定しておく
・相続人全員の名前を記載する
・印鑑証明を受けた実印を押す
なお、不動産であれば所在地や面積、預貯金であれば口座番号などを正確に書くことが重要です。
相続税の申告はどうするの?
相続税の申告は、相続開始日(死亡日)の翌日から10か月以内に亡くなったご家族の住所地の管轄税務署に相続税の申告と納税をします。この期間を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課されることがありますので注意してください。
なお、必ず相続税を納めなければいけないわけではなく、相続する財産が基礎控除を超えなければ相続税を納める必要はありません。
※基礎控除とは、「申告が必要ない」「相続税がかからない」というボーダーラインとなる金額で、以下の計算式で算出した金額です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
専門家に依頼する時のポイントは?
相続手続きや遺産分割協議、相続税の申告について解説してきましたが、自分で手続きするのは大変だと感じた人も多いのではないでしょうか。
特に、初めて相続手続きをする人は大変に感じるかと思います。
さて、相続手続きや遺産分割協議は弁護士や司法書士に依頼するのかな、とイメージしている人もいるかと思います。
それでは、どんな相続手続きの時に弁護士、司法書士に依頼すれば良いのかを解説していきます。
まず、弁護士に相続手続きを依頼するポイントは、遺産相続でトラブルが起こる可能性が高い場合です。理由は、弁護士は法律の専門家の中で、相続人同士でトラブルが発生した時に唯一相続人の代理人になることができるからです。
では、司法書士に相続手続きを依頼するポイントですが、遺産相続でトラブルが起こる可能性が低く、不動産の名義変更(相続登記)をする場合です。
そして、弁護士、司法書士、どちらに相続手続きを依頼するにしても費用は依頼する内容によって変わってきます。弁護士事務所、司法書士事務所のホームページに相続手続きの料金が記載されていることもありますが、最初に相談する時に費用について必ず確認しましょう。
まとめ
相続手続きは自分でできるかどうか、弁護士や司法書士など専門家に依頼するメリットや費用について解説してきました。
死亡届の提出や亡くなったご家族の預貯金の調査など自分でできそうな相続手続きもありますが、遺産分割協議や相続税の申告などは自分で手続きするのは大変かと思われます。
手間と労力を考えると、弁護士や司法書士など専門家に依頼することをおすすめします。