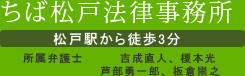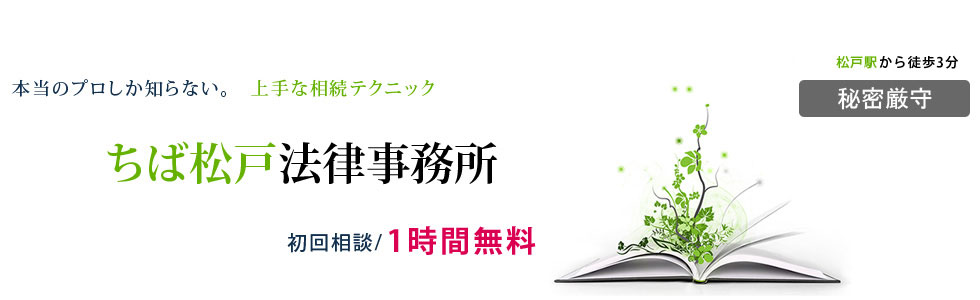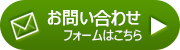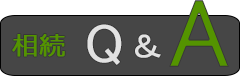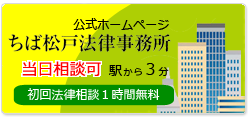遺産分割とは?遺産分割に関するトラブル事例も紹介
家族が亡くなり親族間で相続が発生すると、遺産をどのように分けるかで揉めることがあります。
特に遺産の中に不動産が含まれている場合、ほかの遺産も含めてどうやって相続するのか、当事者間では妥当な解決を導けないケースも多いと思います。
また、相続人の1人が遺産を独り占めしていたり、遺産分割前に勝手に財産を使い込んでいたりした場合、亡くなった方の思いを実現するためにも、早めに適切な対処をする必要があるでしょう。
この記事では、遺産分割の方法・手続きに関して解説したうえで、遺産分割でよくあるトラブルやその解決方法についてわかりやすく解説していきます。
遺産分割とは?
遺産分割とは、亡くなった方の財産をどのように分けるかを決定する手続き全般のことを指します。
相続が発生すると、亡くなった方の財産は、法律で定められた相続分の割合で相続人全員が共有することになります。
共有状態になった財産の管理・処分は、相続人全員の合意を得ておこなう必要があります。そのため、共有状態のまま放置しておくと、遺産を売却する際など、さまざまな面で不便を感じることになるでしょう。
また、時間が経過するとその次の世代にさらに相続が発生してしまい、相続・権利関係が複雑になってしまうおそれがあります。
さらに、相続財産に不動産が含まれている場合、固定資産税の支払いや駐車場代の支払いなど、その不動産を所有している相続人に負担が生じてしまうおそれもあるでしょう。
そこで、相続が発生した場合には、できるだけ早く遺産分割をおこない、相続人間で遺産を分配することが重要になるのです。
4つの遺産分割方法
遺産分割の方法には、主に次の4つの種類があります。
2. 換価分割
3. 代償分割
4. 共有分割
預貯金や現金であれば、相続人で均等に分割するだけで平等に分配できるかもしれません。
しかし、分割に馴染まない財産については、分割方法で揉める場合もあるでしょう。
ここでは、遺産分割でおこなわれる主な分割方法について解説していきます。
現物分割
現物分割とは、遺産を現物のまま分配する方法です。
たとえば、長男が不動産、次男が預貯金、長女が株や有価証券をそれぞれ相続する場合が、現物分割にあたります。
また、遺産の中に土地が含まれている場合、1筆の土地を分筆して、その土地をそれぞれの相続人が相続することになります。
現物分割の場合、全ての相続人に平等に財産を分けるのが難しいケースが多いため、ほかの3つの分割方法が併用されるケースが多いです。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に変えて、それを相続人間で分配する方法です。
換価分割であれば、平等に遺産を分配できるため、相続人間で不満が出にくいのが特徴です。
しかし、財産の処分費用や譲渡取得税などを誰が受け持つかで争いが出ることもあるため、そこまで考慮して分配をおこなう必要があります。
代償分割
代償分割とは、ほかの相続人に対して代償金を支払うことで、相続人の1人が単独で遺産を相続することを認めてもらう分割方法です。
たとえば、長男が遺産を単独で相続する代わりに、次男と長女に一定の金額を支払うことで話をまとめる場合がこれにあたります。
この分割方法は、現物分割が困難な場合に有効な分割方法ですが、代償金の算出方法で揉める場合もあることを頭に入れておく必要があります。
共有分割
共有分割とは、遺産を相続人全員の共有名義にして所有する分割方法です。
相続人全員の共有財産である点で公平感を得られるほか、余計な費用や手間もかからないのが特徴です。
しかし、共有財産を売却する場合には、相続人全員の許可が必要になったり、二次相続が発生した場合に権利関係が複雑になるなど、デメリットも多い分割方法となります。
遺産分割に関する3つの手続き
遺産分割に関する手続きは、主に次の3つです。
● 遺産分割調停
● 遺産分割審判
基本的には、協議→調停→審判の流れで手続きは進んでいきます。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産をどのように分配するかについて、相続人全員でおこなう話し合いのことを指します。
誰がどの遺産を相続するのか、借金がある場合には誰が相続するのかなど、相続に関する事項全てをこの協議で決定します。
ただし、相続人同士の話し合いではお互い感情的になるケースが多く、1度揉めてしまうと交渉が長期化しがちです。
もし、相続人同士の話し合いでまとまらない場合には、遺産分割調停で話し合いをまとめることを検討することになります。
遺産分割調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらい、相続人同士の話し合いによる解決を目指す手続きです。
中立・公正な立場である調停委員が、当事者双方から提出された証拠や主張を精査し、法律の枠組みに沿った適切な遺産分割方法を提示してくれます。
調停に回数の制限はないため、双方納得がいくまで話し合いがおこなわれます。
もし、話し合いでは解決できそうにないと判断した場合には、遺産分割審判を申し立てて、裁判所による判断を仰ぐことになるでしょう。
遺産分割審判
遺産分割審判とは、当事者双方から提出された証拠や主張を精査し、裁判所が遺産の分割方法について決定する手続きです。
話し合いによる合意を目指す手続きではないので、問題を解決しやすくなるのが大きなメリットです。
また、審判で決定した内容は、裁判による判決と同様の効果を持つため、遺産を不当に手放さない者がいた場合、強制的に財産を回収できるようになります。
なお、相続トラブルに精通した弁護士であれば、相続人の財産調査から、遺産分割協議・調停・審判など全ての手続きを一括して任せることができます。
専門書類の収集や遺産分割協議書の作成、連絡の取れない相続人とのやりとりなど、遺産相続にかかる手間を大幅に軽減することができます。
もし、相続トラブルでお困りの場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割でよくあるトラブルと解決方法
遺産分割の場面では、これまで揉めたことがなかった相続人同士で揉めるケースも珍しくありません。
ここからは、遺産分割でよくあるトラブルと、その解決方法について解説していきます。
遺産の範囲が確定していない
亡くなった方の遺産なのか判断できない場合や、判明している以外の遺産が存在する可能性がある場合、遺産分割がスムーズに進まないおそれがあります。
この場合、遺産確認の訴えで遺産の範囲を確定させたうえで、遺産分割協議をおこなうのが良いでしょう。
また、現在判明している遺産だけで遺産分割協議をおこない、もし今後新たな遺産が発見された場合には、その際に再度遺産分割をおこなう旨の約束を取り交わしておくこともできます。
遺産に不動産が含まれている
遺産に土地や建物などの不動産が含まれている場合、不動産の分割方法で揉める場合があります。
前述した通り、遺産分割の方法には4つの種類があるので、それぞれを組み合わせて、相続人全員が納得いく分割方法を模索していくことになります。
また、遺産に含まれる不動産を売却する際の評価方法で揉めた場合、複数の評価方法を組み合わせることで、相続人間で納得できる金額を決定します。
不動産の評価方法は、相続人間でも揉めやすいポイントなので、できれば亡くなる前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺産分割前に遺産を使い込んでいた
遺産分割協議前に、相続人の1人が勝手に財産を使い込んでいた場合には、使い込まれた財産が存在するものとして遺産分割をおこなうことができます(民法906条の2)。
また、使い込まれた遺産の返還請求(不当利得返還請求)や、それによって被った損害について賠償(不法行為に基づく損害賠償請求)を請求することもできます。
なお、どちらの請求にも時効が設定されているため、使い込みが発覚した場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
未成年者の相続人がいる
未成年者は、遺産分割協議をおこなうことができません。そのため、親権者が未成年者の代理人となって遺産分割をおこなうのが原則です。
ただし、親権者と未成年の子どもが相続人になる場合、親権者が自分に優位な遺産分割をする可能性があるため、未成年者の代理人になれません。
この場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらったうえで、遺産分割をおこなうことになります。
高齢で認知症の相続人がいる
高齢で認知症を患っている相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
未成年者と同じように、認知症を患っている相続人は、自分で適切な判断ができない状態です。その状態のまま遺産分割をおこなうのは、その相続人にとって不利益を及ぼす可能性があるため、成年後見人を選任してもらう必要があるのです。
内縁の配偶者がいる
法律上、相続権が認められていない内縁の配偶者がいる場合、自己の取り分が減らされることをおそれたほかの相続人と揉める可能性があります。
内縁の配偶者が相続において不利益を受けないようにするためには、亡くなる前に生前贈与で財産を譲り渡しておいたり、遺言書で内縁の配偶者の取り分をしっかり明記しておくことが大切です。
また、ほかに相続人がいない場合には、特別縁故者として遺産を相続できる場合があります。
亡くなった方を長年介護してきた相続人がいる
亡くなった方を長年介護していたり、家業を手伝ったりしていた相続人がいる場合、「寄与分」としてほかの相続人よりも多くの遺産を相続するのが認められるケースがあります。
また、長年身の回りの世話をしてきたのが亡くなった方の親族であれば、「特別寄与料」として、寄与度に応じた金銭を請求できるケースもあります。
ただし、寄与度の評価については、相続人間で揉める可能性が高い部分でもあるので、もし揉めたら早めに弁護士に相談しましょう。
遺産を独占する相続人がいる
遺産を隠し持っていたり、独り占めしようとしている相続人がいる場合には、遺産分割調停や遺産分割審判で、遺産を適切に分配するよう求める必要があります。
また、もしその相続人が遺産を使い込んでいたような場合には、前述したように、不当利得返還請求や損害賠償請求を起こすことも可能です。
遺言書の内容に偏りがある
特定の相続人に全ての遺産を相続させるなど、遺言書の内容に偏りがあった場合、不利益を被る相続人から遺留分侵害額請求をされてしまう可能性があります。
兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分と呼ばれる相続分を有しています。たとえ、遺言の内容とはいえ、自身の遺留分を侵害された場合には、特定の相続人に対して、遺留分の支払いを請求できる権利を持っています。
遺留分を侵害された相続人としては、遺留分侵害額請求をする余計な手間と時間をかけさせられることになり、感情的な対立が激しくなるおそれがあります。
亡くなった方が、遺留分についてよくわからず遺言書を作成しているケースもあるため、できれば遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスをもらいながら作成するのがおすすめです。
遺言書に遺産分割禁止期間が設定されている
遺言書で遺産分割禁止期間が設定されている場合、原則その期間は遺産分割をおこなうことができません。
たとえば、相続人に未成年者がいる場合には、未成年者が成年になるのを待って遺産分割をしてもらうために、遺産分割禁止期間が設定されることがあります。
ただし、相続開始のときから5年を超える分割禁止期間の設定はできないため、たとえば10年の禁止期間が設定されている場合には、分割禁止期間は5年としてカウントされます。
協議したあとに遺産や遺言書が出てきた
遺産分割の協議がおこなわれたあとに、遺産や遺言書が出てくるケースがあります。
遺産の一部について遺産分割をすることも認められているため、すでに成立している遺産分割が無効になることはありません。この場合、新たに出てきた遺産について、別途遺産分割協議をおこなうことになります。
また、遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合、遺言の内容が優先され、遺産分割協議のやり直しをしなくてはならないのが原則です。
しかし、相続人全員の合意が得られれば、すでに決まった遺産分割協議の内容で相続することも可能です。
なお、遺産や特定の相続人に不利になるような遺言書が故意に隠蔽されていた場合には、すでに決まった遺産分割協議の無効を主張できるケースもあります。
遺産分割をした遺産が他人のものだった
遺産分割で取得した遺産が、亡くなった方の財産ではなかった場合、相続人と第三者の間で揉める可能性があります。
もし、その財産の所有者から返還請求をされた場合、すでに決まった遺産分割が無効になる可能性があるでしょう。
ただし、必ずしも遺産分割が無効になる訳ではなく、第三者に取り戻された財産が遺産の多くを占める場合を除き、当然には遺産分割の効果は失われません。
遺産分割が有効な場合、遺産を失った相続人は、ほかの相続人に対して相続分に応じた支払いを求めることができます。
遺産分割でトラブルが起きた場合の対処法
遺産分割でトラブルが起きた場合の主な対処法は、次の2つです。
● 遺産分割トラブルに精通している弁護士に相談する
遺産分割協議が長期化すると、いつまで経っても財産を処分できず、財産を占有している相続人が不利益を被るおそれがあります。
遺産分割トラブルがあった場合、なるべく早めに次の対処法を試してみましょう。
遺産分割調停や遺産分割審判を活用する
当事者間の話し合いで交渉がまとまらない場合には、遺産分割調停や審判を活用し、第三者を挟んで問題解決を図るのが良いでしょう。
遺産分割調停であれば、経験豊富な調停委員が、相続人全員が納得できるような分割方法を提案してくれます。そのため、話し合いがスムーズにまとまる可能性が高いです。
ただし、遺産分割調停は、あくまでも当事者間の話し合いを前提とした手続きなので、相続人が頑なに自身の主張を曲げない場合、1年経過しても調停がまとまらないケースも珍しくありません。
その点、遺産分割審判であれば、裁判所に妥当な遺産分割方法を決めてもらえるので、トラブルを一定の解決に導くことができるでしょう。
遺産分割トラブルは専門家である弁護士に相談を
遺産分割で揉めた場合には、早めに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割に関するトラブルの場面では、お互い感情的になってしまい、うまく妥協点を見つけられないケースも珍しくありません。
その点、遺産分割を含めた相続問題に精通している弁護士であれば、法律や裁判例を基に、妥当な解決方法を提案してもらえます。
また、ヒートアップしている当事者の間に入ってもらうことで、話し合いを穏便にまとめることもできるでしょう。
遺産分割調停や審判まで対応できる弁護士であれば、全ての手続きを任せることができるため、複雑な相続手続きに関して調べる手間や時間、精神的負担を減らせるのも魅力的です。
弁護士に相談するだけで、請求できないと思っていた財産を請求できる可能性があるため、遺産分割に関するトラブルは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
遺産分割とは、遺産の分配方法を決定する手続きのことで、遺産分割協議・調停・審判などを活用し、相続人間で納得できる遺産分割方法を模索します。
この記事でもご紹介したように、遺産分割の場面ではさまざまなトラブルが想定されます。
法定相続分を適用することで問題を解決できるケースなら話は早いですが、なかには権利関係が複雑になっていて、誰がどれくらい相続すべきなのかがよくわからなくなっているケースも存在します。
1人で間違った対応をしてしまうと、あとから遺産分割の内容を覆せなくなってしまう可能性もあります。
もし、相続に関してお困りごとがございましたら、ちば松戸法律事務所までお気軽にご相談ください。