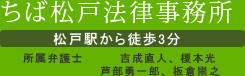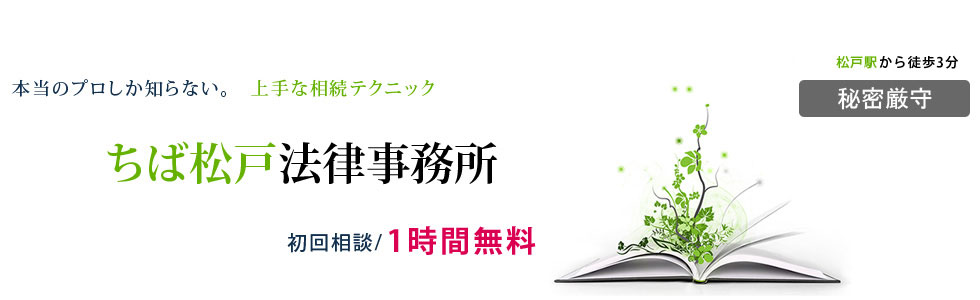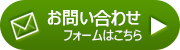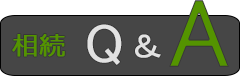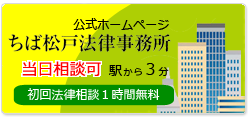親が亡くなったらどこから手を付ければいい?相続の流れと弁護士の役割を解説
急に親を亡くしてしまい、「相続をどうすれば良いかわからない」とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺産相続には、法律で決められた手続きとその期限、その他守らなければならないルールがあります。また、相続手続きは調べること、判断すべきこと、話し合うべきことが多く、どうしても時間がかかってしまうのが一般的です。
そのような場合は、手続きを正確に行うため、より後悔のない相続を行うため、また時間的・心理的負担を軽減するために、弁護士をご活用いただくのも一つだと考えます。
また、すぐに弁護士への依頼には至らなくとも、まずは相続手続き全体の流れを把握しておくだけでも役に立つはずです。
このコラムでは、親が亡くなった場合の相続手続きの流れと、その中で弁護士がお役に立てることを解説します。
1.相続手続き全体の流れ
親が亡くなった場合、相続手続きのおおまかな流れは次の通りです。
各手続きの詳細は第3章で解説します。
② 葬儀の実施・葬儀にかかった費用の整理
③ 遺言書の有無の確認
④ 相続人の確認
⑤ 相続財産・債務の調査、遺産目録の作成
⑥ 相続放棄・限定承認の手続き(希望される場合)
⑦ 準確定申告
⑧ 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
⑨ 相続財産の名義変更
⑩ 相続税の申告
①死亡届の提出、⑥相続放棄・限定承認の手続き、⑦準確定申告、⑩相続税の申告は、それぞれ法律で決められた期限内に行わなければいけません。
また、これらを期限内に完了するためには、その前提となる④相続人の確認、⑤相続財産・債務の調査、⑧遺産分割協議等の手続きをできる限り迅速に行う必要があります。
2.相続で弁護士ができること(包括)
相続手続き全体における弁護士の役割は主に次の4つです。
依頼者様の代理人として各手続きを行うこと
各手続きに付随するサポート(資料集め等)
万が一、揉め事になりそうな場合の円満解決
各手続きで弁護士ができることについては、次章でお伝えします。
ひとまず、弁護士は「相続の代理人」「相続の包括的なサポーター」だとお考えください。
3.各手続きの詳細と弁護士の役割
3-1.死亡届の提出・死体埋葬許可証等の取得
親が亡くなってしまったとき、子どもには死亡届を提出する義務があります。
死亡届とは、亡くなった方の戸籍に死亡の記載をし、住民票を削除するための手続きです。
死亡届の提出先は、亡くなった方の死亡地・本籍地または届け出をする方が所在する市町村役場です。
死亡届の提出に手数料はかかりません。
死亡届を提出するには、まず、医師に死亡診断書(病院で亡くなった場合)または死体検案書(病院以外で亡くなった場合)を作成してもらってください。
死亡届を提出する際は、同時に、火葬許可証や死体埋葬許可証等の申請も行います。これらは、ご遺体の葬儀や埋葬を行うために必要な書類です。
死亡届の提出には期限があります。期限は、届け出をする人が死亡の事実を知った日から7日以内です。
3-2.葬儀の実施・葬儀にかかった費用の整理
親が亡くなった場合、まずは葬儀を執り行うのが一般的かと思います。
ここでご留意いただきたいのは、葬儀にかかった費用の領収書を整理し、保管しておくことです。葬儀費用は、⑩相続税の申告の際、相続した遺産の金額から控除することができます。
3-3.遺言書の有無の確認
被相続人(亡くなった方)の正式な遺言書がある場合、相続は原則として遺言書の内容で指定された通りに行われます。したがって、親が亡くなった後相続について考える際は、まず、遺言書の有無を確認することが最優先となります。
仮に遺言書があった場合はすぐに開封せず、開封前に、まずは弁護士などの専門家に相談するようにしてください。遺言書の種類によっては法律で決められた開封の手続きを踏まなければ、罰則の対象となるリスクがあるためです。
また、形式や書き方に不備があり、遺言書そのものが無効なケースもあります。
弁護士は相続のプロですので、それらの見極めを的確に行うことが可能です。
また、遺言書の内容が著しく不公平であったり、ご自身の法定相続分を侵害するような場合にも、諦めず弁護士へご相談ください。
遺留分減殺請求または遺留分侵害請求等の方法で、そのお悩みを解決できる場合があります。
3-4.相続人の確認
遺言書がない場合、相続財産の分け方は相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。そのための準備として、まずは「誰が相続人になるのか」を確定しなければいけません。
相続人を確定しなければならない主な理由は、次の2点です。
遺産分割の基準となる法定相続分は、「誰が相続人になるか」によって決まる
相続人になるのは、法律で定められた一部の親族です。これを法定相続人と言います。親が亡くなった場合は、亡くなった方の配偶者と子どもが相続人になるのが一般的です。
※親族のうち誰が法定相続人になるかについて、詳しくは『相続の基礎知識』のページをご参照ください。
相続人の確認は、亡くなった親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍)を取り寄せて行います。
相続手続きについて弁護士にご依頼をいただければ、相続人の確定がより迅速かつ確実に行えるようアドバイスや資料収集のお手伝いをさせていただけます。
3-5.相続財産・債務の調査、遺産目録の作成
相続財産を分けるためには、まず、亡くなった親の相続財産(相続財産には借金などの債務も含まれます)に何がどのくらい含まれているのか、それを正確に把握する必要があります。
また、相続財産・債務の状況は、相続放棄や限定承認を行うかどうかを判断する重要な資料にもなります。
調査の方法としては、例えば次のものがあります。
不動産の登記簿を確認する
銀行預金の残高証明書を取り寄せる
負債について、信用情報機関へ情報開示請求する
相続財産・負債の調査には慎重さ・確実さが求められる一方、あとの相続放棄・限定承認の期限を考えると急がなければならないジレンマがあります。
相続手続きを弁護士にご依頼いただければ、これらの調査にも迅速かつ確実に対応させていただけます。
3-6.相続放棄・限定承認の手続き(希望される場合)
相続人は、相続によってかえって損をする場合には、その相続を拒否する手続きをすることができます。これを相続放棄といいます。
また、相続放棄と似た手続きとして限定承認というものもあります。限定承認では、相続で得る財産の範囲内で負債を相続することができ、財産が負債よりも多い場合はその差額を引き継ぐことができます。なお、限定承認を行うには相続人全員の合意が必要です。
※相続放棄と限定承認の手続きについて、詳しくは当事務所コラム『相続放棄とは?メリットとデメリット、注意点を解説』をご参照ください。
相続放棄をすべきかどうかわからない、相続放棄のやり方がわからない、限定承認をしたいが他の相続人の同意を得られないなど、お悩みの方はぜひ弁護士へご相談ください。
具体的な状況に応じて適切なアドバイスが可能な他、ご依頼をいただければ代理人として相続放棄・限定承認の手続きを行うことや、他の相続人の方との話し合いをお引き受けすることも可能です。
相続放棄・限定承認には、いずれも相続の開始があったことを知った時から3カ月以内という期限があります。その期限を過ぎてしまうと、相続人は「全ての相続を引き受ける」と自動的に認定されるためご注意ください。
3-7.準確定申告
準確定申告とは、亡くなった親の確定申告を、子どもたち相続人が代わりに行う手続きです。
準確定申告には期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税の両方が義務付けられています。
3-8.遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
相続人の間で相続財産の分け方を話し合い、決定することを遺産分割協議と言います。
「生前、親に介護や援助をしたので、その分を分割割合に反映して欲しい」等の言い分や、「不動産の分け方をどうするか」といった問題もここで話し合われることになります。
遺産分割協議で後悔のない判断をするためには、相続に関する専門の知識・経験がある方が安心です。また、親族間での話し合いに心理的ストレスを感じる方も多く、その点についてのフォローも考えておいた方が良いでしょう。
ご依頼をいただけましたら、弁護士が相続人ご本人に代わって、遺産分割協議への参加をお引き受け致します。それにより、ご本人が直接親族の方と話し合う必要がなくなります。また、弁護士は依頼者様の代理人として行動しますので、専門知識を活かし依頼者様の利益になるよう話し合いを進めます。さらに、専門家である弁護士が介入することにより、他の相続人の方への主張にも説得力が生まれ、話し合いがよりスムーズにまとまることも期待できます。
無事、相続財産の分け方を合意できたら、その内容を書面(遺産分割協議書)として残しておきます。これは後々の証拠になる他、相続登記等を行う場合の必要書類にもなります。
3-9.相続財産の名義変更
不動産、銀行預金、有価証券等を相続した場合は、それらの名義を親(被相続人)から相続人ご本人名義に書き換えます。
特に、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されるため、不動産を相続された場合は速やかに対応するようにしてください。
3-10.相続税の申告
どの財産をどれだけ相続するのかが確定した結果、相続税の申告が必要な場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告を行う義務があります。同期限内に、申告と納税の両方を行います。
まとめ
以上が、親が亡くなった場合に必要な相続手続きの流れです。
相続手続きは時間と手間がかかる上、親族とお金の話をしなければならない精神的ストレスも伴います。親が亡くなってただでさえご心労の中、それはどなたにとっても大変ではないでしょうか。
相続の専門家の中で唯一、相続人の代理人になれるのが弁護士です。ご依頼をいただけましたら、相続の手続きや親族の方との話し合いを、弁護士が代わりに引き受け、依頼者様ご本人の利益のために遂行致します。
また、弁護士は紛争解決のプロでもあります。万が一、相続に関して親族間で揉めごとが起きてしまいそうな場合、弁護士が間に入っていればできるかぎり円満かつスムーズに事態を収め、裁判や事態の長期化・複雑化を回避することもできます。
親が亡くなり相続でお困りの際は、ご本人のご負担を軽減しつつ後悔のない相続を行うため、まずは弁護士へのご相談をおすすめします。