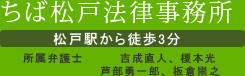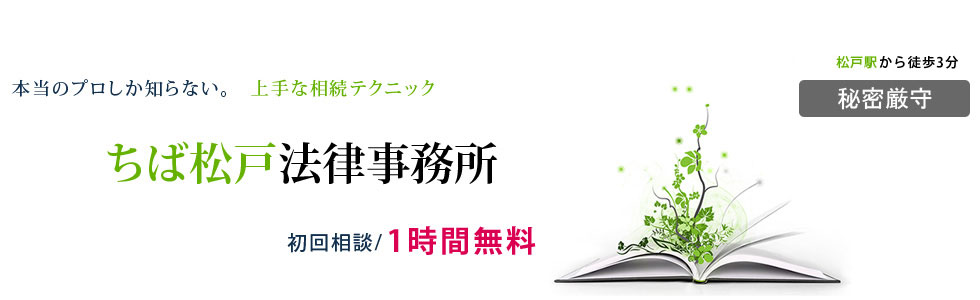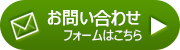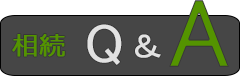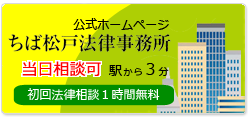終活で知っておきたいこと。自分らしい最期を迎えるために準備すべきこと5選
人生100年時代と言われ、長生きをする高齢者は増えてきています。「自分の判断力があるうちに残された家族のために準備をすること」が終活です。
終活すると言われても何をしたら良いか悩んでしまいます。そこで、今回は終活の準備すべきことを5つのテーマで解説します。
エンディングノートを作ろう
エンディングノートとは、「自分が亡くなった後、家族が困らないように自分の考えや要望をまとめたノート」です。遺言書と違い法的拘束力もなく、家族に伝えたいことを自由に書いて問題ありません。
ただ、自由に書いて良いと言われても何を書けば良いのか困ってしまいますので、書いた方が良いことをいくつか紹介します。
①家族構成
自分を中心に、両親、兄弟(兄弟の配偶者も)、配偶者、子、孫まで書いておくことをおすすめします。これは、残された家族が相続人調査をする時に、エンディングノートを見て疎遠の親戚が判明するなど役立つこともあるからです。
②資産状況
エンディングノートに資産状況を書くことは、財産調査をする時に役立ちます。預貯金、不動産、株式、借金についても詳細に書くことをおすすめします。
それでは、エンディングノートに書く時のポイントをいくつか紹介します。
【預貯金】
金融機関名、支店名、口座番号、届出印の保管場所などを書きます。なお、電気、ガスなど公共料金を毎月引き落とししている口座はどれかもわかるように書きましょう。
特に、ネットバンクはキャッシュカードしか発行されない場合もあり、残された家族が気づかないこともありますので忘れずに書くようにしましょう。
【不動産】
不動産は、現在所有している物件の数、種類(土地、戸建て、マンションなど)、用途(自宅、事務所など)、物件の住所、エンディングノートを書く時点の評価額などを書きます。
【株式】
株式は、取引のある証券会社、口座番号、保有株式銘柄などを書きます。最近はネット証券を使用している人もいますが、ネット証券は残された家族が気づかないこともありますので、取引している証券会社の欄に忘れずに書くようにしましょう。
【借金】
借金は家族に言いたくないこともありますが、借金もマイナスの財産として残された家族に相続されますので、忘れずに書くようにしましょう。
書く内容は、金融機関など借入先の名前、エンディングノートを書く時点の借入額、返済期間などです。
エンディングノートはネット上で検索すると、簡単な作り方や印刷してすぐ使用できるフォーマットも多いので、ネット上で一度探してみると良いでしょう。
また、デジタル終活についてもエンディングノートに書くことをおすすめしますが、これは後ほど詳しく解説します。
遺言書を作ろう
遺言書は、「誰にいくら相続したいか」など自分の死後の意思を伝えるための文書です。相続では家族間のトラブルが発生することもありありますので、終活では遺言書を作ることも重要です。
遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言はすべて自分で書きます。ただ、2019年1月13日から財産目録だけはパソコンや代筆で作ることができるようになり便利になりました。また、2020年7月10日から自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度が始まりました。自筆証書遺言書保管制度を使えば、家庭裁判所の検認が必要なく、遺言書の改ざん、紛失を防ぐことができます。保管手数料は3,900円となります。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言書を作成し、公証人、遺言者、証人2人の同席の上で署名、捺印します。そのため、遺言書の内容や意思能力についてトラブルになることはあまりありません。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証人、証人2人の同席の上、自分で封印した遺言書を提出して、公証人が署名、捺印します。自筆証書遺言と違い、遺言書をパソコンで作成でき、内容も秘密にできます。そして、遺言書を作成したことを明らかにすることができます。
ただ、公証役場で遺言書を保管するわけではないので、紛失などの危険性はあります。また、家庭裁判所の検認が必要になります。
不要な財産の整理しよう
自分が亡くなった後、残された家族に負担をかけないように預貯金、不動産などの整理をしておくと良いでしょう。財産整理のポイントをいくつか紹介します。
①預貯金の整理
銀行口座を複数持っていると、残された家族が相続手続きをする時に大変です。公共料金や年金の受け取り口座、貯蓄用の口座などできるだけ最小限の数にまとめておくと良いでしょう。
②クレジットカードの整理
クレジットカードを複数枚、しかも年会費数万円以上のクレジットカードを持っている人もいるかと思いますので、そのような場合はできるだけ最小限の数にまとめておくと年会費を抑えることができて良いでしょう。
③株式の整理
株式投資をしている人もいるかと思いますが、残された家族が株式投資をしないのであれば、売却して現金化した方が管理が楽になります。
④不動産の整理
不動産は物件が多いと相続する時に手間がかかります。どうしても残しておきたい物件だけ残しておき、それ以外の物件は売却して現金化しておくと相続する時に家族の負担が減ります。 売却以外には生前贈与などもありますが、贈与税が発生しますので不動産の整理を検討する時は専門家に相談してみるのも良いでしょう。
⑤自動車の整理
自動車は高齢になると乗る機会が減るかと思います。運転免許証を返納するタイミングで売却することを検討するのが良いかと思います。
デジタル終活をしよう
最近、「デジタル終活」という言葉を聞くようになりましたが、デジタル終活とは「自分のパソコンやスマートフォンのデータを生前に整理すること」です。
それでは、デジタル終活について解説していきます。
①デジタルデータの断捨離
デジタル終活では、デジタルデータを「いるもの」と「いらないもの」に分けます。まず、使っていないが毎月何となく支払っているサブスクリプションは解約すると良いでしょう。また、残された家族に見られたくないようなメールやSNSのダイレクトメッセージなどは削除します。お葬式に呼んでほしくない友人などの電話帳も事前に削除するのが良いでしょう。
②デジタル終活するものを一覧表にする
代表的なものは、写真、動画、電話帳、ネットバンク、ネット証券のID・パスワード、SNSのアカウント、航空券や旅行サイトなどのID・パスワードなどです。
一覧表は例えば、エクセルやワードで作成して印刷した紙をエンディングノートに貼るのが良いかと思います。エクセルやワードで作成するのが苦手な人は、一覧表のメモ書きをエンディングノートに貼ってまとめておくのが良いかと思います。
葬儀とお墓の終活
自分が亡くなった後に、葬儀やお墓のことを残された家族に任せることは家族の負担になります。そこで、葬儀とお墓の終活についてもいくつか紹介します。
①葬儀のことを考える
最近だと家族葬を行う人が増えてきていますが、まずは参列者名簿を作り、宗教・宗派を決めます。先祖代々、決められたお寺で葬儀や法要を行っている場合もありますので、このような場合は自分が亡くなった後、家族同士のトラブルならないように事前に調整することが重要です。
②お墓のことを考える
生前にお墓を用意することは、自分の気に入ったお墓を選ぶことができ、残された家族がお墓を用意する費用を減らすことにもなります。また、生前に用意したお墓は相続税の対象にならないため、節税効果もあります。
ただ、先祖代々決められたお墓に入ることが家族のルールになっている場合もありますので、このような場合は自分が亡くなった後、家族同士のトラブルならないように事前に調整することが重要です。
まとめ
終活について知っておきたいことを5つのテーマで解説しました。今回解説したことを参考にすれば、自分の最期を迎えるため、そして残された家族の負担が軽くなると思います。無理せずコツコツと終活を進めてみてください。